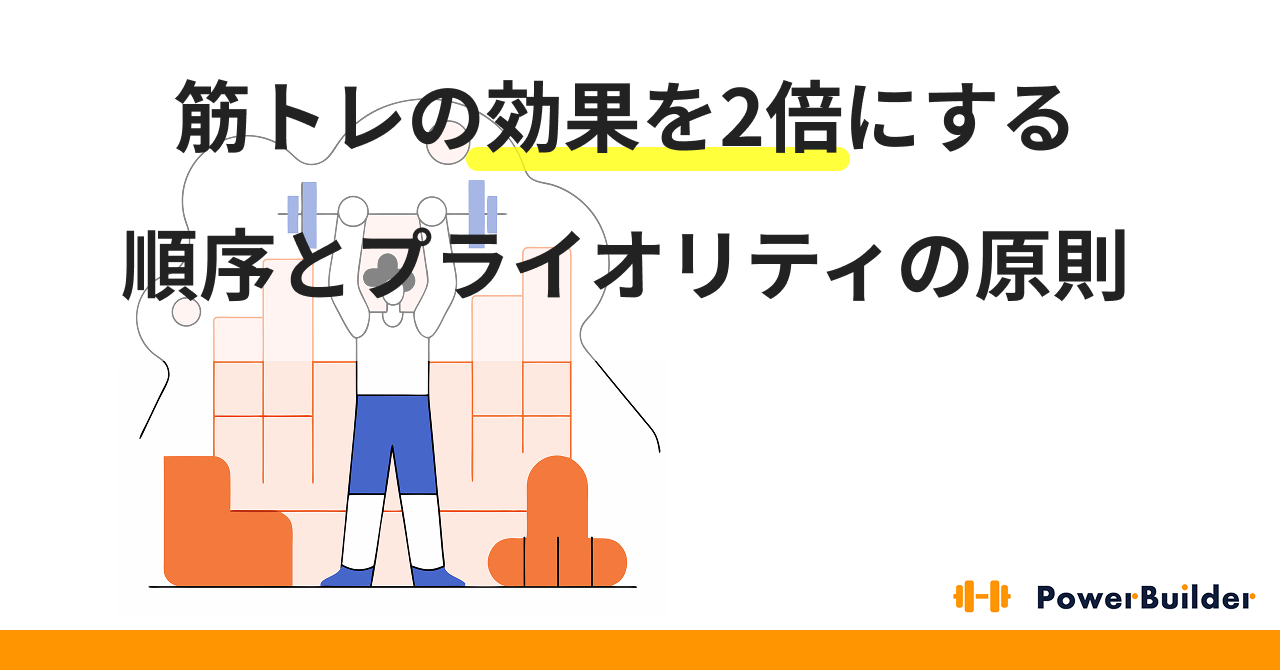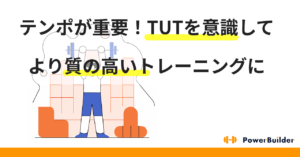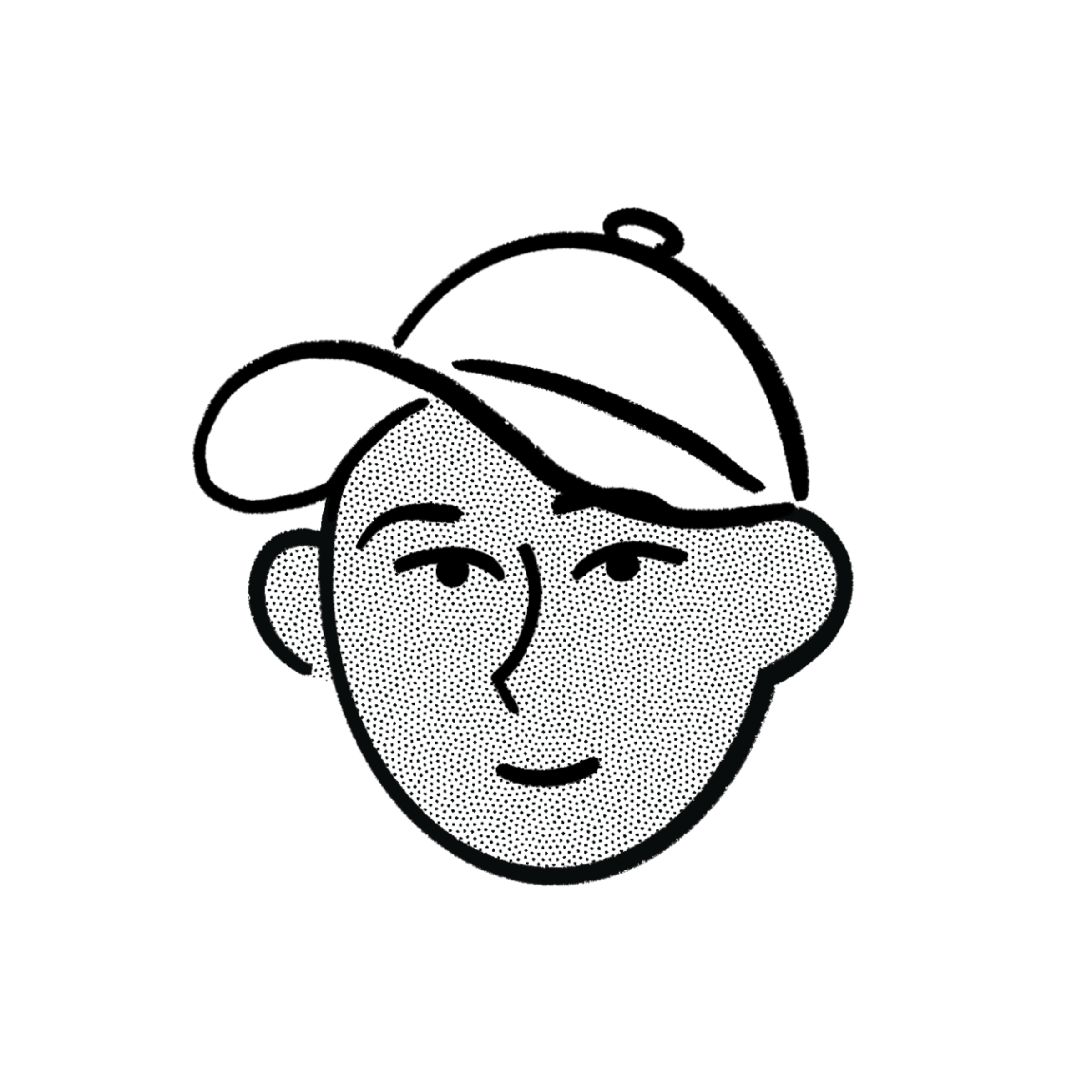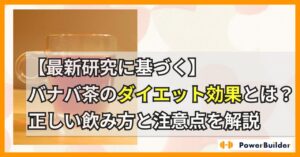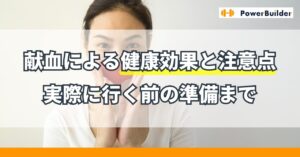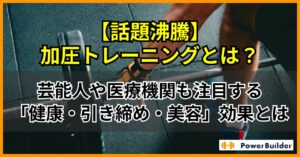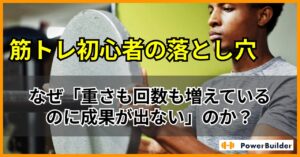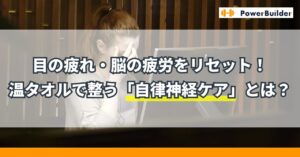筋トレやフィットネスを頑張っているけれど、「思ったほど効果が出ない…」と感じたことはありませんか? 実は、トレーニングの「順序」を工夫するだけで、同じメニューでも効果に大きな差が生まれます。今回は、トレーニングの効果を最大限に引き出す「順序の考え方」と、目標に最短で近づくための「プライオリティの原則」について解説します。
トレーニングの順序はなぜ重要なのか?
筋トレには多くの種目がありますが、順番を無視してやみくもに取り組んでしまうと、筋肉が十分に刺激されなかったり、疲労が先に来てしまい正しいフォームを維持できなかったりと、効果が半減してしまうことがあります。
基本的な原則としては、以下の順序が効果的とされています。
1. 多関節運動から単関節運動の順で行う
ベンチプレスやスクワットのように2つ以上の関節を使う種目を多関節種目といいます。これは関節を複数使うことで、メインターゲットとなる筋肉と補助筋を使って動作を行います。複数の筋肉で協力し合うため、動員される筋肉が多くなることで持ち上げる総重量が増え、筋肉に大きな負荷をかけることができます。
ダンベルフライやレッグエクステンションのように1つの関節のみを使う種目を単関節種目といいます。使う関節が一つのため、より一つの筋肉にターゲットを絞ってピンポイントで鍛えることができます。確実にメインターゲットの筋肉に負荷をかけられますが、使う筋肉が絞られることで、持ち上げる重量は多関節種目に比べ下がりやすい特徴があります。
まずは多関節種目で大きな力をかけてトレーニングを行い、単関節種目でピンポイントで鍛えると効果的ということになります。
2. 大きな筋肉から小さい筋肉の順でトレーニングを行う
一般的に大きな筋肉とは、大胸筋、広背筋、大腿四頭筋や大臀筋、ハムストリングスなどが挙げられます。例えば上腕三頭筋のような比較的規模の小さな筋肉を先にトレーニングすると、ベンチプレスを行う際に重たい負荷をかけにくくなり、大胸筋への刺激が弱くなります。さらに上腕三頭筋が疲労していることで胸の筋肉を刺激しにくくもなります。
そのため上半身では、大胸筋や広背筋などの大きな筋肉から上腕二頭筋や上腕三頭筋などの小さな筋肉の順でトレーニングするのが基本的なルールとなります。
3. フリーウエイト、マシンの順で行う
フリーウエイトとマシンでは基本的にフリーウエイトを先に行うようにしましょう。フリーウエイトではバランスを取ったり、身体をコントロールする能力が必要となります。他のマシン種目で身体が疲労した状態だと、身体のコントロールがしづらくなり効率が落ちやすくなります。
4. さらに知っておきたいポイント
上半身や下半身をバラバラで行うのではなく、同じ部位の種目を続けて行うことで、筋肉に強く刺激を入れることができます。また腹筋などの体幹の種目は最後に行うようにしましょう。体幹部分が疲労すると、他のトレーニング種目で姿勢が安定しにくくなり、効率が悪くなります。
以上を踏まえたトレーニング例

上半身トレーニング例
- ベンチプレス(胸)多関節種目
- マシンフライ(胸)単関節種目
- ラットプルダウン(背中)多関節種目
- アームカール(腕)単関節種目
- フレンチプレス(腕)単関節種目
- クランチ(体幹)単関節種目
下半身トレーニング例
- スクワット(脚)多関節種目
- マシンレッグプレス(脚)多関節種目
- レッグカール(脚)単関節種目
- カーフレイズ(脚)単関節種目
プライオリティの原則とは?
さらにおさえておきたいのが「プライオリティの原則(Priority Principle)」です。これは、最も鍛えたい部位・伸ばしたい能力をトレーニングの最初に持ってくるという考え方です。筋トレに限らず、スポーツやスキル練習にも応用される重要な原則です。
人間の集中力や体力はトレーニングの序盤が最も高いため、そこで「重点を置きたい部分」にエネルギーを集中させることで、成長スピードが格段にアップします。
例えば、胸の筋肉を大きくしたい人やベンチプレスの重量を伸ばしたい人は、ウォームアップ後すぐにベンチプレスから開始します。反対に、腕の太さを優先したいなら、アームカールなどの種目を前半に持ってくるというアプローチもあります。自分にとって自分の目的を叶えるトレーニングや種目を優先するということになります。
プライオリティの原則は、1日のメニューだけでなく、1週間のスケジューリングにも応用できます。たとえば、週の最初(月曜日など)に一番鍛えたい部位を設定し、疲れが少ない状態で集中して取り組むのも、非常に効果的です。
まとめ
トレーニングの順序は、単なる「流れ」ではなく、成果を大きく左右する「戦略」です。エネルギーの高い序盤に重要な種目を配置し、最も鍛えたい部位に優先的に取り組むことで、筋肉の発達スピードも変わってきます。プライオリティの原則を活用して、自分だけの最適なトレーニングメニューを構築していきましょう。