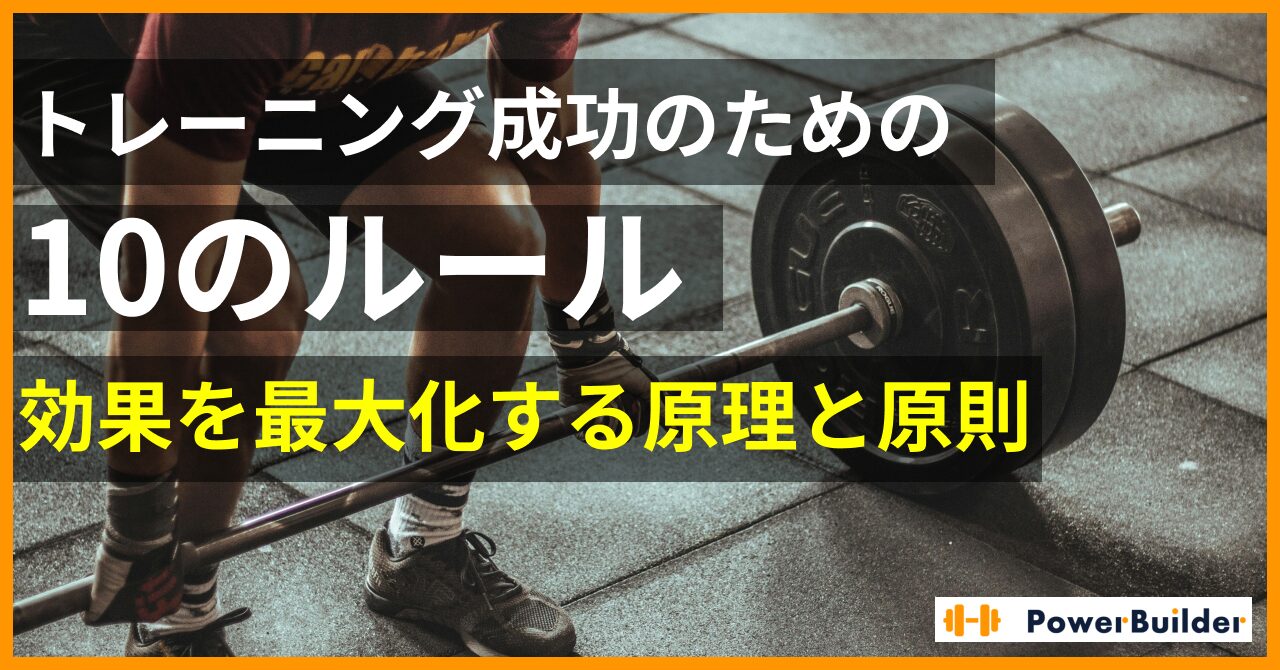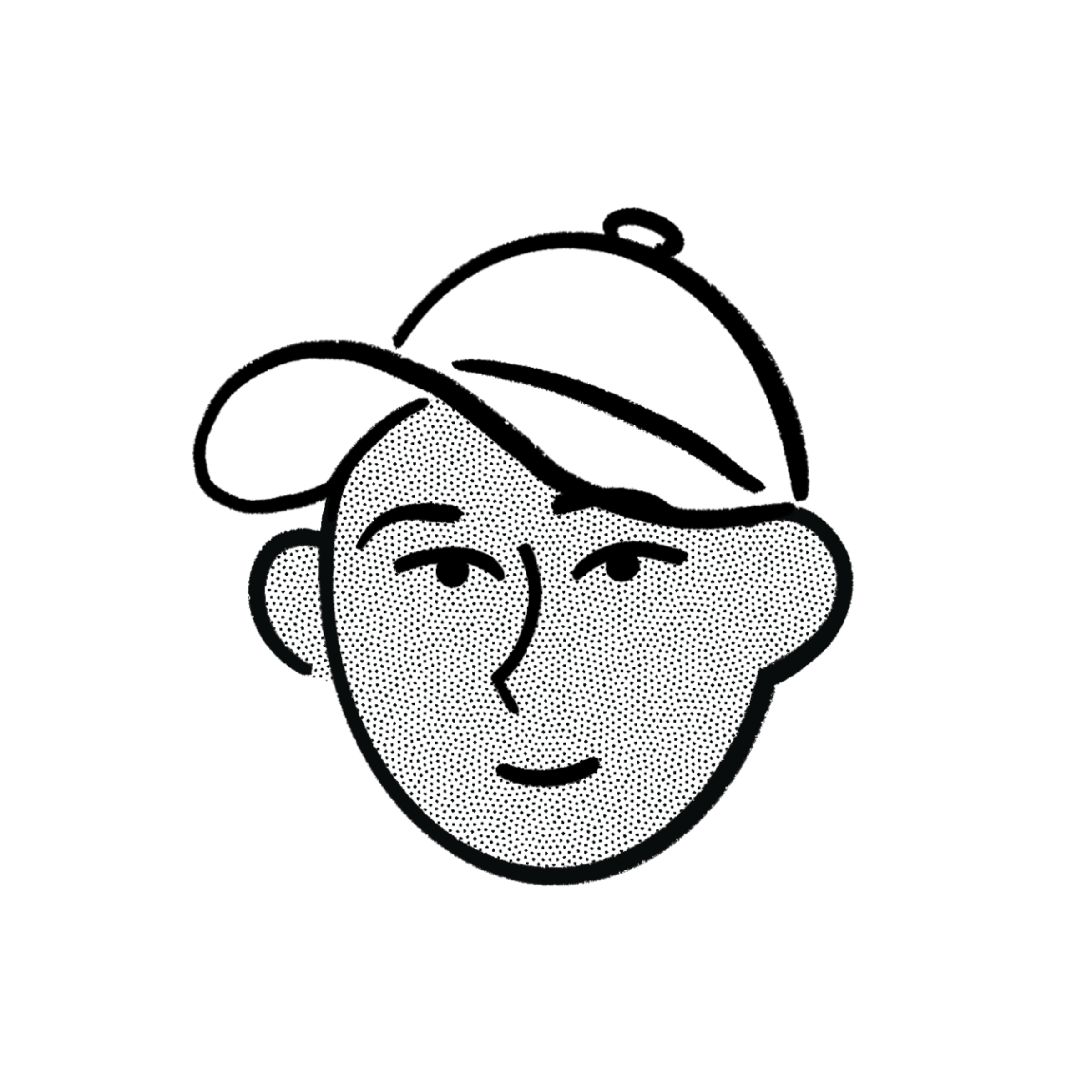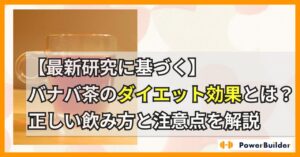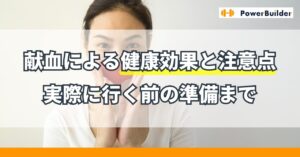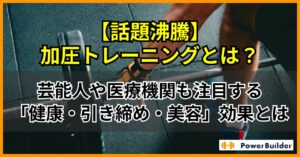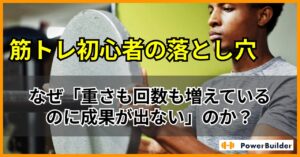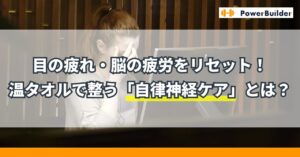トレーニングで理想の体を手に入れるためには、ただやみくもに運動するのではなく、科学的な視点で効果を最大化することが重要です。
特に「トレーニングの原理・原則」を理解し、実践することで、効率的に筋力アップやダイエットが可能になります。本記事では、トレーニングの基本となる「5つの原理」と「5つの原則」について詳しく解説します。
1. トレーニングの「5つの原理」
① 過負荷(オーバーロード)の原理
筋肉を成長させるには、日常生活で受ける負荷より強い負荷をかける必要があるという原理です。
毎日階段を100段登る生活をしている人が、トレーニングを始めた際にそこでかかっている負荷よりも低い水準の負荷でトレーニングをしてもトレーニングにおける効果は無いということです。
例えば10回ギリギリ持ち上がるような重量設定でトレーニングをすれば日常動作で10回で動作が出来なくなるような負荷はほとんどなく、筋肉に対して過負荷をかける事が出来ます。
また同じ重量や回数でトレーニングを続けても、筋肉はそれに慣れてしまい成長が停滞します。少しずつ負荷を上げる(重量を増やす・回数を増やす・セット数を増やす)ことで、筋肉を成長させることができます。
② 特異性の原理
鍛えた部位や運動の種類によって得られる効果が異なるという原理です。例えば、持久力を向上させたいなら有酸素運動、筋力をつけたいなら無酸素運動を行ということです。また、スポーツ競技のパフォーマンス向上を目的とするなら、競技に近い動きを取り入れることが重要です。
例:
• 胸の筋肉をつけるならベンチプレスやペクトラルフライ
•サッカー選手なら、瞬発力を高めるためのスプリントやアジリティトレーニング
•登山に強くなりたいなら、長時間歩く持久力トレーニング
間違った例:
•脚の筋力をつけたいのでウォーキングやジョギングを行う、ウォーキングやジョギングは脚の筋力において日常生活レベルの強度しか得られない為、一般的には筋力アップや筋肉量アップの効果は得られない。
③ 可逆性の原理
トレーニングをやめると、得た効果が失われるという原理です。筋力や持久力は継続的にトレーニングしなければ、徐々に低下していきます。長期間運動を休むと、せっかく鍛えた筋肉が減少し、パフォーマンスが落ちてしまいます。
対策:
•週に1回でもいいので、最低限の運動を継続する
•怪我や忙しい時期でも、短時間の運動を取り入れる
•仮に運動をやめてしまっても一度得た水準までの筋肉量や筋力、体力レベルまでは戻しやすい(マッスルメモリー)。一度トレーニングをやめてしまってもまた新たに開始することが重要。
④ 漸進性の原理
トレーニングの負荷は段階的に上げるべきという原理です。急に高強度の運動をすると怪我のリスクが高まります。無理のない範囲で徐々に強度を上げることが、安全かつ効果的なトレーニングにつながります。
例:
•初心者は軽い負荷でフォームを習得し、徐々に重さを増やす
•長距離ランニングの初心者は、まず短い距離から始める
⑤ 個別性の原理
トレーニングの効果には個人差があるという原理です。年齢、性別、体質、運動経験、生活習慣などによって、最適なトレーニング方法は異なります。他人と比較せず、自分に合ったプログラムを作ることが重要です。
例:
• YouTubeなどで発信されているものは根拠が無いものも多く、あくまで発信者が成功したトレーニングであり全員が当てはまるとは限りません。またどのレベルのに向けた内容かが分からないものも多い
• 初心者がいきなりアスリート並みのトレーニングをしたりすると怪我のリスクが高まる
• 体力のある人はそれに見合った強度負荷でトレーニング、初心者は軽い負荷から段階的に強度を上げていく

2. トレーニングの「5つの原則」
① 全面性の原則
全身をバランスよく鍛えることが重要という原則です。特定の部位ばかり鍛えると、筋力のバランスが崩れ、怪我のリスクや慢性的な痛み、各関節が正常にはたらなくなり、身体の機能が低下しパフォーマンスが下がる可能性もあります。
例:
•腕や胸の筋肉だけでなく、脚や背中、体幹も鍛える
•筋肉の裏と表、右と左、上半身、下半身などをバランスよくトレーニングすることが大事
•筋トレと有酸素運動をバランスよく行う
② 意識性の原則
トレーニングの目的を明確にし、狙った筋肉を意識することで効果が高まるという原則です。ただ漠然と運動するのではなく、どの筋肉を使っているかを意識すると、より効果的なトレーニングが可能になります。
このマシン種目は何のためにトレーニングし、何処の筋肉が使われ、行なっている最中も、狙っている筋肉の伸び縮みを感じ意識します。
さらに筋肉を意識する為にはフォーム作りがとても重要になります。いくら胸の筋肉を意識してトレーニングを行っても、腕を優先的に使ってしまう間違ったフォームでは胸を意識する事も効率よくトレーニングをすることはできません。
筋肉には起始と停止(付着部と付着部)が存在し、筋肉の走行から付着部どうしが離れたところから近づく、トレーニングフォームは筋肉が伸ばされた状態から筋肉の走行に合わせて縮めていく事が重要です。
例:
•スクワットでは「太ももとお尻の筋肉を意識する」
•腹筋トレーニングでは「お腹に力を入れてゆっくり動作を行う」
• 腕立て伏せは名称的に腕のトレーニングと思われがちですが、フォームや意識で胸の筋肉を効率よくトレーニングすることが出来る。腕のトレーニングという認識で行っている段階で腕のトレーニングが意識されやすくなる。
※またスポーツや競技者のトレーニングの場合、使用する筋肉を意識しすぎなくても良い場合もある。(走る動作の際に大腿四頭筋や大臀筋などの筋肉の伸び縮みを意識して走る人はいない為)
③ 漸進性の原則(原理にも含まれる)
トレーニングの負荷を徐々に上げていくことが大切です。
仮に筋肉に過負荷を与えても、同じ回数、同じ重さでしばらくトレーニングをしていると、筋肉にとっては日常的な負荷に変わってしまいます。トレーニングは同じ負荷でずっとトレーニングせずに段階的に強度を上げましょう。
④ 個別性の原則(原理にも含まれる)
人によって最適なトレーニング方法が異なるため、自分に合ったプログラムを作ることが重要です。
体格、骨格、姿勢、性別、性格、スポーツ歴、病歴、目的などを考慮する必要があります。
⑤ 反復性の原則
継続しなければ効果は出ないという原則です。1回のトレーニングでは大きな変化は生まれませんが、継続することで体は確実に変化していきます。定期的に体重計に乗ったり、体の変化を写真に収めて変化を見比べたり、細かい変化を楽しみながら行なってみましょう。
例:
•毎週2~3回の運動を続けることで、少しずつ体力が向上する
•ダイエット目的なら、食事管理と運動をセットで継続する
3. まとめ
トレーニングの原理・原則を理解することで、効率的に体を鍛え、理想の結果を得ることができます。
✅ 「5つの原理」(トレーニングの基本ルール)
• 過負荷の原理: いつもより強い刺激を与える
• 特異性の原理: 目的に合った運動をする
• 可逆性の原理: 継続しないと効果が失われる
• 漸進性の原理: 徐々に負荷を上げる
• 個別性の原理: 自分に合った方法を選ぶ
✅ 「5つの原則」(効果を高めるポイント)
• 全面性の原則: 全身をバランスよく鍛える
• 意識性の原則: 筋肉を意識して動作を行う
• 漸進性の原則: 無理なく強度を上げる
• 個別性の原則: 自分に合ったトレーニングをする
• 反復性の原則: 継続することが最も重要
このルールを守りながら行うことでトレーニングの効果が向上する。またトレーニングの効果をあまり感じられない時にはこのルールを守りながらトレーニング出来ているかもう一度考えてみましょう。これらを意識しながら、自分に合ったトレーニングを継続し、理想の体を目指しましょう!